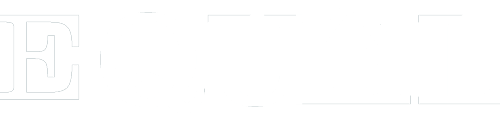新築住宅ができるまでの流れ!基礎~上棟の工程をご紹介
- 公開日
- 2022.06.24
- 更新日
- 2022.06.24

こんにちは!悠悠ホームEQUALです!家づくりを検討している方の中には、今から家づくりを始めたらどれくらいの期間がかかるのだろうか?といった疑問をお持ちの方もいるのではないのでしょうか?家を建てる工事といっても、基礎工事や建て方、屋根工事、外構工事などいろいろな工程があります。
今回は新築住宅ができるまでの流れについてご紹介いたします。家づくりを始めたての方にはぜひ知っておいていただきたい知識となるので、最後まで読んでみてください!
基礎工事完了後の上棟までの流れ
設備先行配管工事
住宅を建築するにあたり、住宅本体工事も重要ではありますが、水道・電気・ガス・通信などのライフラインを維持するための
設備工事も重要となってきます。宅地の調査をするときに調べるポイントに、
①水道メーター
②排水枡
③電柱
の位置確認があります。これらのライフラインを維持する為の外部から敷地内への入口を把握して、住宅の設計を始めます。一般的には建物本体のまわりの外部の配管工事を先行させ、基礎完成後に、外部からの配管と内部の配管を繋ぎます。その後に木工事(建て方)に入っていきます。この先行工事の事を「外部先行配管」と言います。
土台敷込
土台敷きとは、基礎コンクリートの上に土台や大引を設置していく作業です。基礎も大事な工程ですが、この土台敷きやこのあとの構造部分は住宅の骨組みとなる大変大事な工程です。
今は、プレカット工場で予め加工された材料が運ばれてきます。加工された材料を現場で組み立てるだけだと考えている方もいらっしゃいますが、現実はそうではありません。
昔ほどではないものの、現場での作業も多くてミスが起こると欠陥住宅を生んでしまいます。土台敷きの工程としては、まず、立上りコンクリートの上にキソパッキンを敷きます。キソパッキンは、 床下の換気を良くすると共に、基礎と土台の縁を切り、コンクリートが吸った湿気を土台に上げない役目があります。
次に、キソパッキンの上に土台を敷き、大引を組みます。大引きとは土台と土台の間を鋼製束で支えられる木材のことを指します。
土台防蟻
土台に使用する木材に薬剤を散布して、防蟻処理していきます。シロアリ対策に欠かせない工程のひとつです。
床合板張り
土台と土台の間に断熱材を敷き込み、その上に床合板を敷き込みます。床合板とは、フローリングの下に張ってある構造用の厚い板の事で、 通称ネダレス合板とも言います。
また、大引きの上から直接に合板を張り付ける工法を根太レス工法(=剛床工法)と言います。根太レス工法では、床面を一体化させるので、水平性を高め、地震や台風時に受ける床面の「横揺れ」や「ねじれ」を抑える効果があります。
棟上げ工事
家の骨組みを組み立てる工事です。棟上げの日は朝から作業を始め、1階の柱から屋根に至るまですべての骨組みを、1~2日で作りあげます。この日だけは、他の現場の大工さんたちを招集して手伝ってもらうほどの、大掛かりな作業です。棟上げ工事が完了後、構造体検査を受けて、上棟となります!
以上で上棟までが完了です。この後はいよいよ外壁や内装の工事に入っていきます。こちらは次回の記事でご紹介いたします!
まとめ
いかがでしたか?今回は「新築住宅ができるまで②」についてご紹介しました。
ぜひ家づくりの参考にしてみてください!
悠悠ホームEQUALでは、高性能な二階建ての注文住宅が1,000万円台から実現します。注文住宅4,500棟の中から厳選したプレミアム大評判プランを無料公開中です!福岡・佐賀エリアでのお家づくりは悠悠ホームEQUALにお任せください!!
他のコラムを見る
-
![【断熱に最重要のサッシ】トリプルガラスの空気層やLow-Eによる価格や性能の違いをご紹介]()
【断熱に最重要のサッシ】トリプルガラスの空気層やLow-Eによる価格や性能の違いをご紹介
-
![【断熱に最重要のサッシ】ペアガラスの空気層やLow-Eによる価格や性能の違いをご紹介]()
【断熱に最重要のサッシ】ペアガラスの空気層やLow-Eによる価格や性能の違いをご紹介
-
![【断熱に最重要のサッシ】木製サッシの価格や性能、メリットとデメリットをご紹介]()
【断熱に最重要のサッシ】木製サッシの価格や性能、メリットとデメリットをご紹介
-
![【断熱に最重要のサッシ】樹脂サッシの価格や性能、メリットとデメリットをご紹介]()
【断熱に最重要のサッシ】樹脂サッシの価格や性能、メリットとデメリットをご紹介
-
![【断熱に最重要のサッシ】複合サッシの価格や性能、メリットとデメリットをご紹介]()
【断熱に最重要のサッシ】複合サッシの価格や性能、メリットとデメリットをご紹介
-
![【断熱に最重要のサッシ】アルミサッシの価格や性能、メリットとデメリットをご紹介]()
【断熱に最重要のサッシ】アルミサッシの価格や性能、メリットとデメリットをご紹介
-
![【最大100万円の補助金】こどもみらい住宅支援事業が見直し]()
【最大100万円の補助金】こどもみらい住宅支援事業が見直し
-
![新築住宅ができるまでの流れ!上棟~竣工の工程をご紹介]()
新築住宅ができるまでの流れ!上棟~竣工の工程をご紹介
-
![新築住宅ができるまでの流れ!着工~基礎の工程をご紹介]()
新築住宅ができるまでの流れ!着工~基礎の工程をご紹介
-
![住宅会社に資料請求をおこなうメリットとデメリットをご紹介]()
住宅会社に資料請求をおこなうメリットとデメリットをご紹介
-
![【最大100万円の補助金】こどもみらい住宅支援事業が延長]()
【最大100万円の補助金】こどもみらい住宅支援事業が延長
-
![土地探しのコツはあるの?失敗しないための考え方をご紹介]()
土地探しのコツはあるの?失敗しないための考え方をご紹介